近年、健康志向の高まりとともにごぼう茶が注目を集めています。便秘改善やダイエット効果が期待され、多くの方に愛飲されているごぼう茶ですが、すべての人に適しているわけではありません。体質や健康状態によっては、注意が必要な場合もあります。
この記事では、ごぼう茶を避けるべき人の特徴や飲む際の注意点について詳しく解説します。安全にごぼう茶を楽しむために、ぜひ参考にしてください。

執筆者:
布袋農園 運営責任者 稲葉 浩太
野草茶・ハーブティー・薬膳茶を研究し、美味しく健康効果の高いお茶を求め日本各地を訪ねている専門家。
腸内細菌の遺伝子検査によるアドザイザーも行っており、「健康は腸から、腸は食物繊維から、食物繊維はお茶から」が口癖。
パーソナル薬膳茶マイスター、パーソナルヘルス協会認定パーソナル腸活コーチ、経営学修士
ごぼう茶とは
ごぼう茶は、ごぼうの根を乾燥させて焙煎し、お茶として楽しむ健康茶です。独特の香りと風味が特徴で、自然派志向の方を中心に人気が広まっています。
粉末のごぼう茶は、ポリフェノールがたっぷりな皮部分も含めて加工しているため特におすすめです。
ごぼう茶の基本的な情報
ごぼう茶は、ごぼうの根を細かく切り、乾燥・焙煎して作られます。栄養価が高く、特に食物繊維のイヌリンが豊富に含まれており、便秘改善や腸内環境の整備に効果があるとされています。
また、ポリフェノールやフラボノイドなどの抗酸化成分も含まれており、老化防止効果も期待されています。カフェインフリーなので、夜間でも安心して飲めるのも魅力の一つです。
作り方は比較的簡単で、市販のティーバッグを使用するか、自宅で手作りすることも可能です。手作りの場合は、ごぼうを細かく切って天日干しやフライパンで乾燥させ、焙煎してからお湯で煮出します。
ごぼうの歴史
ごぼうの薬用利用の歴史は非常に古く、中国の伝統医学において重要な位置を占めていました。明代の本草学の集大成である『本草綱目』(16世紀)には、ごぼうの種子(牛蒡子・ごぼうし)が記録されており、解毒作用や利尿作用、発汗作用を持つ生薬として高く評価されていました。のどの腫れや風邪の初期症状を鎮める薬としても用いられ、中国では現在も漢方薬の材料として活用されています。
日本には奈良時代(8世紀頃)に伝わったとされ、当初は薬草として栽培されていました。平安時代の文献にもごぼうが登場しており、宮中や寺院で薬用植物として利用されていたことがうかがえます。特に、腸を整える働きや利尿作用が重宝され、民間薬としても広まりました。
江戸時代になると、ごぼうは徐々に食用として普及していきます。土壌に深く根を張るごぼうは日本の風土と相性が良く、栽培もしやすかったため、庶民の食卓に取り入れられるようになりました。煮物や汁物、漬物など幅広い料理に利用され、「きんぴらごぼう」などの郷土料理もこの頃に生まれています。
このように、ごぼうは中国では主に「薬」として、日本では「薬用から食用へ」と独自の発展を遂げてきた植物です。現在では日本を代表する根菜の一つとして、健康効果と食文化の両面から私たちの生活に深く根付いています。
そして現代では、古来からの薬効が改めて注目され、ごぼう茶という形で健康維持や美容をサポートする飲み物として広く親しまれるようになりました。
ごぼう茶の主な成分

ごぼう茶の健康効果は、含まれる様々な有効成分によるものです。主要な成分とその働きを見ていきましょう。
食物繊維(イヌリン)
ごぼうに豊富に含まれる水溶性食物繊維「イヌリン」は、プレバイオティクスとして働き、腸内の善玉菌(特にビフィズス菌)のエサとなります。腸内環境が整うことで便通がスムーズになり、便秘改善に役立ちます。また、腸内フローラが健全化されると、免疫力の向上や肌荒れ改善にもつながります。
さらに、イヌリンは糖の吸収をゆるやかにする働きがあるため、食後血糖値の急上昇を抑制する効果があり、糖尿病予防や肥満対策にも有効です。水溶性食物繊維は水を含んでゲル状になることで満腹感を与えるため、食べ過ぎ防止やダイエットサポートとしても注目されています。
ポリフェノール(クロロゲン酸)
ごぼうに含まれるポリフェノールの一種「クロロゲン酸」は、強力な抗酸化作用を持つ成分として知られています。体内で発生する活性酸素を取り除き、細胞の老化や生活習慣病のリスクを軽減します。
また、クロロゲン酸には血糖値の上昇を抑える作用があり、食事から摂取した糖が急激に吸収されるのを防ぐため、糖尿病予防に役立ちます。抗炎症作用もあるため、慢性的な炎症が関わる動脈硬化や肥満、肌荒れなどの改善にも効果が期待できます。さらに、脂質代謝をサポートし、脂肪の蓄積を抑える働きがある点でもダイエットや生活習慣病対策に有用です。
ミネラル類
ごぼうには亜鉛、鉄、マグネシウムといったミネラルがバランス良く含まれています。
・亜鉛 は細胞分裂や新陳代謝に欠かせないミネラルで、髪や肌の健康維持、免疫機能の向上に重要です。不足すると味覚障害や皮膚トラブルが起こることもあるため、日常的に補うことが大切です。
・鉄 は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。鉄分が不足すると貧血や疲労感の原因になるため、特に女性にとってはごぼう茶からの補給が有効です。
・マグネシウム はエネルギー代謝や神経の働きに関与し、筋肉の緊張を和らげる効果もあります。ストレスや偏った食生活で不足しやすいため、日常的に摂ることで心身の安定にもつながります。
これらのミネラルは単独ではなく相互に働くことで、血液循環を促進し、冷え性や肩こりの改善にも貢献します。
ごぼう茶の効果と効能
ごぼう茶には多くの健康効果が期待されています。主な効果について詳しく見ていきましょう。
便秘改善
ごぼう茶の最も代表的な効果の一つが便秘改善です。豊富な食物繊維、特にイヌリンが腸内の善玉菌であるビフィズス菌の活動を助け、腸内環境を整えます。
イヌリンは水分を吸収し、腸の内容物を柔らかくする働きもあるため、便通がスムーズになります。朝食前に飲むことで、腸の動きを活発にし、より効果的に便秘改善が期待できます。
ダイエット効果
ごぼう茶はダイエットにも効果的です。食物繊維が満腹感を与えるとともに、脂肪の吸収を抑制する働きがあります。また、ポリフェノールが脂質代謝を改善し、脂肪燃焼を促進します。
カロリーが低く、代謝を上げる効果もあるため、食前に飲むことで自然に食事量を減らすことができます。血糖値の上昇も抑えるため、太りにくい体質づくりにも役立ちます。
その他の健康効果
便秘改善やダイエット以外にも、ごぼう茶には様々な健康効果があります。抗酸化作用により細胞の老化を防ぎ、血圧の安定化にも寄与します。
肝臓の働きをサポートするデトックス効果や、血液循環の改善効果も報告されています。さらに、免疫力向上効果もあり、季節の変わり目や風邪予防にも活用できます。
ごぼう茶の味
ごぼう茶はそのままでは独特な風味を持っています。最初は土のような香りを感じることがありますが、その後にほのかな甘さが続きます。ポリフェノールの影響で軽い渋みを感じることもあります。
美味しいごぼう茶の肝は、なんといっても焙煎です。焙煎の程度によって味わいが変わるのも特徴で、深煎りは香ばしく、浅煎りはフレッシュな風味が楽しめます。布袋農園のごぼう茶はこだわりの溶岩焙煎!遠赤外線効果で焦げ感が無く香ばしさだけを感じることができます。
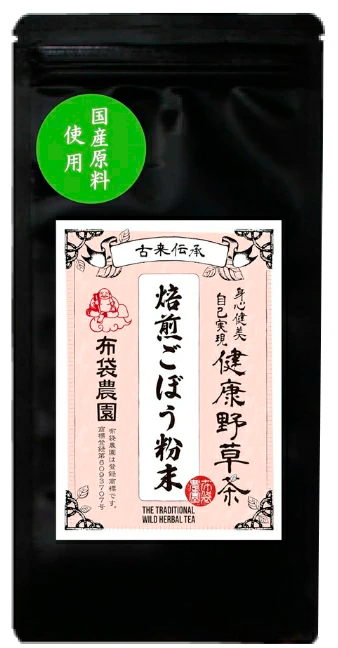
ごぼう茶を控えた方がよいケース

ごぼう茶は多くの健康効果が期待できますが、以下のような方は注意が必要です。
キク科アレルギーがある人
ごぼうはキク科に属する植物です。そのため、キク科(ヨモギ、ブタクサ、ヒマワリなど)に対してアレルギーを持つ方は、ごぼう茶でも同様のアレルギー症状を起こす可能性があります。具体的には、かゆみや発疹、鼻水、目のかゆみ、まれに呼吸困難といった症状が現れる場合があります。
過去にキク科の植物でアレルギー反応が出たことがある方は、ごぼう茶の摂取を控えるか、まずはごく少量から様子を見てください。不安がある場合は、事前に医師へ相談するのが安心です。
女性ホルモンと関係する疾患を持つ人
ごぼうには植物性エストロゲン(女性ホルモン様の作用を持つ成分)が含まれるとされており、ホルモンバランスに影響を与える可能性があります。特に、乳がんや子宮筋腫、子宮内膜症など、女性ホルモンの影響を受けやすい疾患を持つ方は注意が必要です。
これらの疾患を治療中の方や過去に診断を受けたことがある方は、ごぼう茶を日常的に摂取する前に必ず主治医に確認しましょう。健康のために飲むつもりが、思わぬリスクにつながる場合があるため、安全性を優先することが大切です。
肝臓や腎臓に問題がある人
肝臓や腎臓に疾患がある方は、ごぼう茶の摂取に注意が必要です。これらの臓器は体内の解毒や老廃物の排出に重要な役割を果たしており、機能が低下している場合、通常は無害な成分でも負担となる可能性があります。特に腎臓に問題がある方は注意が必要です。ごぼうにはカリウムが含まれており、腎機能が低下している場合、カリウムの過剰摂取は危険な状態を引き起こすことがあります。
また、肝機能が低下している際は解毒作用が弱くなっているため、ポリフェノールなどの成分が体に負担をかける可能性もあります。肝臓や腎臓に疾患がある方は、医師と相談してから摂取を検討してください。
特定の薬を服用している人
薬を服用中の方は、ごぼう茶との相互作用に注意が必要です。ごぼう茶に含まれるポリフェノールや食物繊維が、薬の吸収や効果に影響を与える可能性があります。特に抗凝血薬を服用している方は注意が必要です。ごぼう茶に含まれる成分が血小板の働きを抑える効果を持つ場合があり、同時に服用すると過剰に血液が薄まるリスクが考えられます。
薬を常用している方は、ごぼう茶を飲む前に必ず医師や薬剤師に相談し、安全性を確認してから摂取するようにしてください。
アレルギー体質の方や不安がある方は、医師に相談してから摂取を検討することをおすすめします。
ごぼう茶に関する注意点と副作用

ごぼう茶を安全に楽しむために、知っておくべき注意点があります。
過剰摂取のリスク
どんなに健康に良いとされる飲み物でも、過剰摂取は体に悪影響を与える可能性があります。ごぼう茶も例外ではありません。
イヌリンの過剰摂取は、下痢や腹痛、腹部膨満感などの消化器症状を引き起こす可能性があります。また、食物繊維の摂り過ぎは、他の栄養素の吸収を阻害することもあります。
特に普段食物繊維をあまり摂取していない方が急に大量のごぼう茶を飲むと、腸が過度に刺激されて不快な症状を引き起こすことがあります。
飲む量と頻度の目安
ごぼう茶を健康的に楽しむための適切な摂取量は、1日1〜2杯が目安です。この量であれば、多くの方が安全に飲用できます。
摂取頻度については、毎日飲む必要はありません。週に3〜4回程度でも十分に健康効果を実感できます。体調や個人差を考慮しながら、自分に合ったペースを見つけることが大切です。
初めて飲む方は、まず週に1〜2回、1杯から始めて、体の反応を見ながら徐々に回数を増やしていくのがおすすめです。
ごぼう茶の正しい飲み方
ごぼう茶の効果を最大限に引き出すための正しい飲み方をご紹介します。
おすすめのタイミング
ごぼう茶を飲む最適なタイミングは、目的によって異なります。便秘改善が目的の場合は、朝起床後すぐに飲むことで腸の動きを活発にし、1日をスッキリと始められます。ダイエット効果を期待する場合は、食事の30分前に飲むことをおすすめします。食物繊維が満腹感をサポートし、自然に食事量を減らすことができます。
リラックス効果を求める場合は、夕方や夜のリラックスタイムに飲むのが良いでしょう。カフェインが含まれていないため、就寝前でも安心です。
日常生活への取り入れ方
ごぼう茶を無理なく日常生活に取り入れるには、自分のライフスタイルに合ったタイミングを見つけることが重要です。朝のルーティンに組み込む場合は、起床後や朝食時に1杯飲む習慣をつけるのがおすすめです。仕事や家事の合間のブレイクタイムに飲むことで、リフレッシュ効果も得られます。
夕食後のリラックスタイムに飲むことで、1日の疲れを癒し、翌日に向けて体をリセットする効果も期待できます。
大切なのは継続することです。無理のない範囲で習慣化し、長期的に健康をサポートしていきましょう。
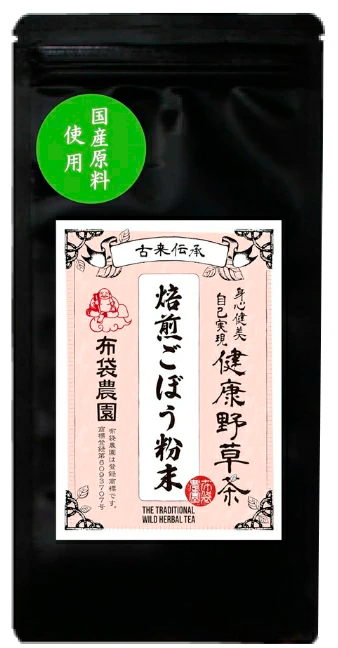
ごぼう茶のメリットとリスクを理解して安全に楽しむ
ごぼう茶は便秘改善やダイエット効果など、多くの健康効果が期待できる優れた健康茶です。しかし、キク科アレルギー、女性ホルモンと関係する疾患を持つ方、肝臓・腎臓に疾患がある方、特定の薬を服用中の方、食物アレルギーがある方は注意が必要です。
適切な摂取量(1日1〜2杯)を守り、体調や体質に合わせて飲むことで、安全にごぼう茶の恩恵を受けることができます。不安がある場合は医師に相談し、自分に最適な飲み方を見つけてください。
正しい知識を持って適切に摂取すれば、ごぼう茶は日々の健康維持に役立つ心強いパートナーとなるでしょう。自然の恵みを活かしたごぼう茶で、より健康的な生活を始めてみませんか。
健康野草茶の布袋農園


